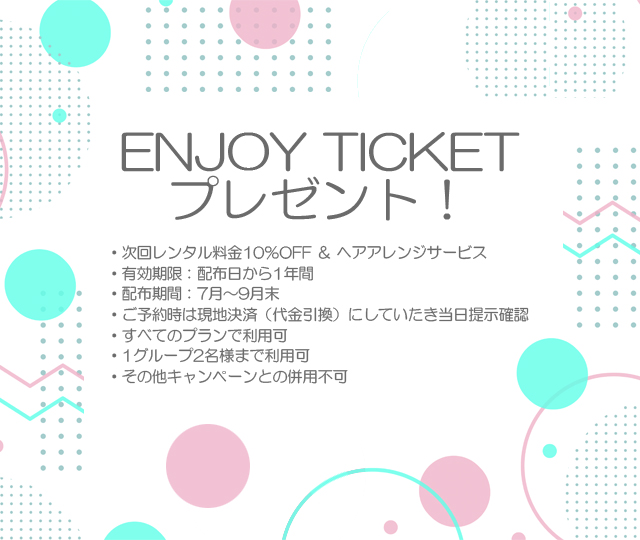京都・晴明神社 Photo:京都フリー写真素材
京都・晴明神社 Photo:京都フリー写真素材
9月下旬は、厳しい残暑が感じられつつも、秋の気配が本格化し始める時期です。
この時期の京都では、夏の賑やかさが落ち着き、古都のもつ静謐な魅力と、秋の訪れを告げる優雅な祭事があります。

晴明祭:晴明神社
京都・晴明神社「晴明祭」(2023年9月23日 京都市上京区) “Seimei Festival” at Seimei Shrine in Kyoto
京都の北部に位置する晴明神社では、陰陽師・安倍晴明を祀る例祭「晴明祭(せいめいさい)」が9月22日、23日に開催されます。
宵宮の22日には、夕刻から提灯行列が行われ、夜には五穀豊穣と無病息災を祈る古式ゆかしい湯立神楽が催され、翌23日の神事当日には、八乙女(はつとめ)や鼓笛隊が練り歩く行列もあります。
この祭事の最大の魅力は、陰陽道という日本独自の神秘的な世界観を肌で感じられる点で、揺らめく提灯が織りなす夜の光景は幻想的で、湯立神楽は、日本のスピリチュアルな側面や、古来より人々の間で育まれてきた信仰心を体感できる行事です。
見学は無料ですが、湯立神楽は1,000円の有料拝観になります。
【晴明祭概要】
- 開催期間:毎年9月22日・23日
- 入場料:無料
- アクセス
京都市バス9・12・67系統「一条戻橋・晴明神社前」下車すぐ。
地下鉄烏丸線「今出川駅」下車、徒歩12分。 - 公式サイトURL:https://www.seimeijinja.jp/
櫛まつり:安井金比羅宮
京都・安井金比羅宮「櫛まつり」(2023年9月25日 京都市東山区) “Kushi Festival” at Yasui Konpira Shrine in Kyoto
安井金比羅宮(やすいこんぴらぐう)では、毎年9月下旬に「櫛まつり(くしまつり)」が開催されます。女性の髪に感謝を捧げ、美を追求してきた日本の歴史を体現する祭事です。
神事のあと、安井金比羅宮から祇園周辺を巡行する「時代風俗行列」が見どころ。多くの観光客を魅了します。
行列に参加する女性たちは、日本髪の歴史を彩る様々な髪型や衣装に身を包み、大原女(おおはらめ)や淀君(よどぎみ)、嵯峨野の尼(さがののあま)といった、歴史上の人物の姿を再現します。
この行列は単なるパレードではなく、髪を大切にしてきた日本女性の美意識と文化の集大成として、日本の伝統的な美の変遷を視覚的に伝える絶好の機会となっています。
見学は無料で、祇園の中心部にある安井金比羅宮が会場となるため、アクセスは非常に便利です。狭い路地を歩く行列は、華やかな衣装や精緻な髪型を間近で鑑賞できます。
【櫛まつり概要】
- 開催期間:毎年9月29日
- 入場料:無料
- アクセス
京都市バス58・80・207系統「東山安井」下車、徒歩1分。
京阪本線「祇園四条駅」下車、徒歩10分。 - 公式サイトURL: http://www.yasui-konpiragu.or.jp/
秋の特別公開と展覧会
9月下旬は、祭礼だけでなく、普段は公開されていない寺院の塔頭や美術館の特別展も楽しめる時期です。
大徳寺の塔頭である興臨院や泉屋博古館などでは、9月下旬から12月にかけて秋季特別公開が行われます。
これら、禅の思想が息づく枯山水庭園や、緻密な美が凝縮された美術品の鑑賞は、祭りの賑やかさとは対照的な、静謐で落ち着いた文化体験ができる機会です。
興臨院 特別公開
興臨院 大徳寺 京都の庭園 Korin-in Temple Daitoku-ji The garden of Kyoto Japan Full HD
【興臨院 特別公開 概要】
- 開催期間:公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
- 入場料:大人800円、中高生400円、小学生300円(保護者同伴)
- アクセス
京都市バス206系統「大徳寺前」下車、徒歩約5分。
地下鉄烏丸線「北大路駅」下車、徒歩15分。 - 公式サイトURL: https://kyotoshunju.com/temple/daitokuji-kohrinin/
泉屋博古館 特別展
ミュージアムのちから Vol.3 泉屋博古館
【泉屋博古館 特別展 概要】
- 開催期間:公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
- 入場料:一般1,500円、学生800円が目安
- アクセス
京都市バス5系統「東天王町」下車、徒歩3分。
地下鉄東西線「蹴上駅」下車、徒歩10分。 - 公式サイトURL: https://sen-oku.or.jp/